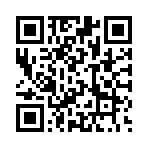2022年03月07日
サドベリー教育って??
今読んでいる本「おはなしワクチン」は、
お子さんの「不登校」で悩んでいる保護者のみなさんはもちろん、
日本に住んでいるほとんどすべての人に一読願いたい・・・(筆者の「はじめに」より)
本です

ということで、興味のある方はぜひ読んで欲しいと思いますが、
今日はこの本の著者・蓑田雅之さんの息子さんが通っていたという、
「サドベリースクール」をご紹介したいと思います
(本でも紹介されています )
)
サドベリー教育とは??
1960年代にアメリカのサドベリーバレーという土地にとても「ユニーク」な学校が誕生!
どこがユニーク?
・授業がない(カリキュラムがない)
・子どもたちを教える先生がいない(スタッフに見守られている)
・子どもたちは、一日中好きなことをやって過ごしている

(散歩の途中、池に石飛ばしをして遊ぶ子どもたち)
この学校の教育理念は「子どもは学びたくなった時に、一番よく学ぶ!」というもので、
大人が教えたり、意図的に導いたりすることは、かえって子どもの学ぶ力を奪う事になる と。
と。

(学びの多い、お店屋さんごっこ!)
だから、この学校では子どもに対して「教えるということを一切しないそうです
でも、子どもは「好きなことをやってもいいよ!」といわれて喜ぶのははじめのうちで、
際限なく自由な環境に置かれると、しだいにやることがなくなって退屈しはじめます!
そして、「自分は何がしたいのか」「何をすべきなのか?」というテーマとむきあわざるをえなくなるのです!
(しいのもりの子どもたちが、よく「ひま~!」というのが、まさにこの時期なんですね )
)
そして、子どもたちは真の学びに目覚めていく!というのです。
子どもは「読み・書き」を教えてもらわなくても、不思議なことに自然と読み書きは身についてきます!
「この字はなんて読むの?」という素朴な疑問から、文字や文章を学びたくなります
この「学びたくなる力」こそが、将来の「生きる力」に結びついていくのですね
そうなんです
これまで、しいのもりでやってきたことが「サドベリー教育」そのものなんだ と、改めて気づき、とても嬉しくなりました~
と、改めて気づき、とても嬉しくなりました~
サドベリー教育とは?
ある意味、従来の公教育とは正反対のポジションにあると言えるかもしれません
だからこそ、しいのもりは「学校に行けない・行かない子」たちにとって、
とても魅力的に見えるのかもしれませんね
お子さんの「不登校」で悩んでいる保護者のみなさんはもちろん、
日本に住んでいるほとんどすべての人に一読願いたい・・・(筆者の「はじめに」より)
本です


ということで、興味のある方はぜひ読んで欲しいと思いますが、
今日はこの本の著者・蓑田雅之さんの息子さんが通っていたという、
「サドベリースクール」をご紹介したいと思います

(本でも紹介されています
 )
)サドベリー教育とは??
1960年代にアメリカのサドベリーバレーという土地にとても「ユニーク」な学校が誕生!
どこがユニーク?
・授業がない(カリキュラムがない)
・子どもたちを教える先生がいない(スタッフに見守られている)
・子どもたちは、一日中好きなことをやって過ごしている

(散歩の途中、池に石飛ばしをして遊ぶ子どもたち)
この学校の教育理念は「子どもは学びたくなった時に、一番よく学ぶ!」というもので、
大人が教えたり、意図的に導いたりすることは、かえって子どもの学ぶ力を奪う事になる
 と。
と。
(学びの多い、お店屋さんごっこ!)
だから、この学校では子どもに対して「教えるということを一切しないそうです

でも、子どもは「好きなことをやってもいいよ!」といわれて喜ぶのははじめのうちで、
際限なく自由な環境に置かれると、しだいにやることがなくなって退屈しはじめます!
そして、「自分は何がしたいのか」「何をすべきなのか?」というテーマとむきあわざるをえなくなるのです!
(しいのもりの子どもたちが、よく「ひま~!」というのが、まさにこの時期なんですね
 )
)そして、子どもたちは真の学びに目覚めていく!というのです。
子どもは「読み・書き」を教えてもらわなくても、不思議なことに自然と読み書きは身についてきます!
「この字はなんて読むの?」という素朴な疑問から、文字や文章を学びたくなります

この「学びたくなる力」こそが、将来の「生きる力」に結びついていくのですね

そうなんです

これまで、しいのもりでやってきたことが「サドベリー教育」そのものなんだ
 と、改めて気づき、とても嬉しくなりました~
と、改めて気づき、とても嬉しくなりました~
サドベリー教育とは?
ある意味、従来の公教育とは正反対のポジションにあると言えるかもしれません

だからこそ、しいのもりは「学校に行けない・行かない子」たちにとって、
とても魅力的に見えるのかもしれませんね